──Web屋が語る、“そこには踏み込めない”という誠実さ
「お問い合わせフォームをつけたいです」というご相談の次に、よく聞かれるのが
「じゃあプライバシーポリシーも作っておいてもらえますか?」という一言です。
一見、気軽なお願いのように思えますが、実はここには
**“Web制作では対応しきれない一線”**が存在します。

お問い合わせフォームなどで個人情報を取得する場合、個人情報保護法に基づき、利用目的などを明示する必要があります。
Webサイトの場合、それを明示する方法として一般的なのが「プライバシーポリシーの掲載」です。
「じゃあ書いておきますね!」と軽く受けられそうですが、これは実はかなりグレーな対応です。
なぜなら、**個人情報の扱い方をどうするかは、運営者自身の意思・業務内容に関わること**だからです。
これを制作会社が勝手に書く=**“法律に関する助言”にあたる可能性**があり、弁護士法の観点で問題となることがあります。
現実には、「プライバシーポリシーも一緒に書いておきましたよ」という制作会社さんも存在します。
もしきちんとリスクや責任の説明があり、それを了承の上での対応なら問題はありません。
でも、中には**説明もなく“おまけ”的に書いてしまうケース**もあるのです。
特にコロナ禍以降、Web未経験から独立した制作者も増え、知識が浅いまま「とりあえず書いておいた」対応も見受けられます。
また、お客様が内容をよく分かっていないことを前提に、**説明の手間を省いて“分からないならこれでいいでしょ”と片づけるような対応**も、残念ながらゼロではありません。
私たちNido.では、法律に関わる部分には踏み込みません。
それは、“できない”のではなく、“踏み込むべきではない”と考えているからです。
もちろん、ひな形の紹介や参考URLのご案内は可能ですし、Googleフォームなどを利用する場合は、**Googleのプライバシーポリシーを引用・リンクする**といった方法もあります。
でも、最終的にその内容を確認し、責任を持つのは運営者=あなた自身であるべきなのです。
プライバシーポリシーって、「書かなきゃいけないから、とりあえず用意する」というイメージがあるかもしれません。
でも本当は、それが**あなた自身を守る盾になるかもしれない**という視点で考えてみてほしいのです。
個人情報を取り扱うというのは、便利な反面、必ず責任が発生します。
だからこそ、“なんとなく作っておく”ではなく、意味を理解した上で、自分の運営に合わせて整える。
それが、これからのWeb運営において必要な考え方ではないでしょうか。
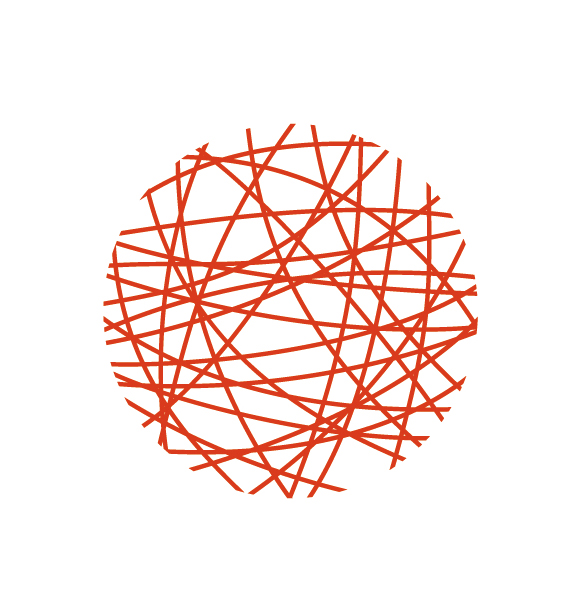
石川県を拠点に、富山県在住のWeb制作者。東京でも中堅どころの制作会社にて部長・執行役員を歴任後、独立。小規模事業者向けサブスク制作サービス「Nido.Growth」を運営。制作の現場から経営までの実務経験をもとに、Webの設計思想や考え方をお届けしています。