──地元密着・経済圏への想い

地元密着。よく聞く言葉ですが、私たちにとってそれは戦略ではなく「思想」です。
Nido.は、地域の事業者に寄り添い、そこで生きる人の声を届けるWeb屋でありたいと考えています。
今回は、地域をベースに仕事をすることの意味と、そこでの“助ける”という定義について書いてみます。
「助ける」という言い方は、仕事を受ける立場からすると少し生意気に聞こえるかもしれません。
けれど私たちは、お客様を下に見る意味ではなく、同じ目線で同じ目標を目指す“パートナー”でありたいと思ってこの言葉を使っています。
Webに不慣れな方の「不安」や「分からなさ」に、横に立って向き合う。
その姿勢こそが、私たちが考える“助ける”という行為です。
良い商品、良い人柄、良いサービス──でも「知られていない」。
Webに触れる機会が少ない世代や事業者はまだ多く、都心と地方では“情報の発信力”に大きな差があります。
都市圏の企業が出す広告やサイトは、自然と洗練されている。
地方では“遅れている”のではなく、“機会が少ない”だけ──この差を埋めたいと思っています。
Web制作は単なる“費用”ではなく、“地域を活性化させるための装置”だと私たちは考えています。
地元企業が自分の言葉で発信できれば、その地域全体に循環が生まれる。
「安く作る」ことではなく、「活かせる形で作る」こと。
Nido.では、自走できるシンプルな仕組みづくりを大切にしています。
都心の企業とは違い、“会いに行ける距離”があるのが地方の強みです。
修正対応や相談、更新のたびに「いつでも話せる人がいる」ことは、大きな安心につながります。
「つくる」ことが目的ではなく、「伝わる」までを支援することが、Nido.の役割です。
Nido.が大切にしているのは、“制作”を通じた関係性の構築です。
地元で営まれる仕事を、その人の言葉で、その地域の空気感のまま、きちんと届ける。
それは単なる「Web制作の仕事」ではなく、地域の力を信じて、循環をつくる行為だと思っています。
助ける、という姿勢で臨むことで、助け合える関係が育っていく。
それが、地方でWeb屋を続ける意味だと、私たちは考えています。
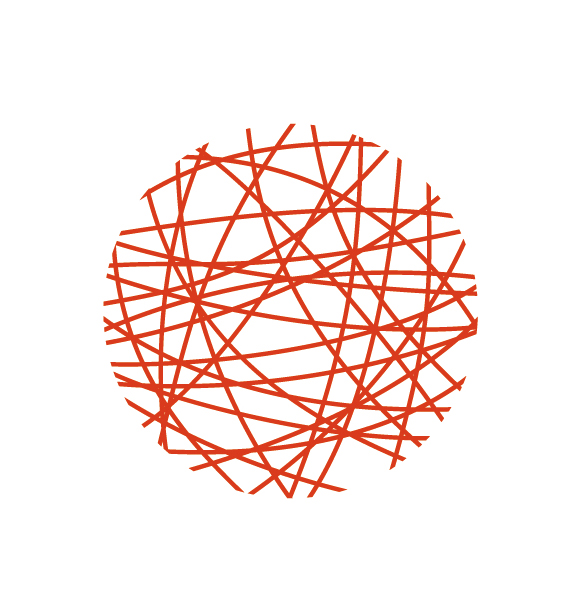
石川県を拠点に、富山県在住のWeb制作者。東京でも中堅どころの制作会社にて部長・執行役員を歴任後、独立。小規模事業者向けサブスク制作サービス「Nido.Growth」を運営。制作の現場から経営までの実務経験をもとに、Webの設計思想や考え方をお届けしています。